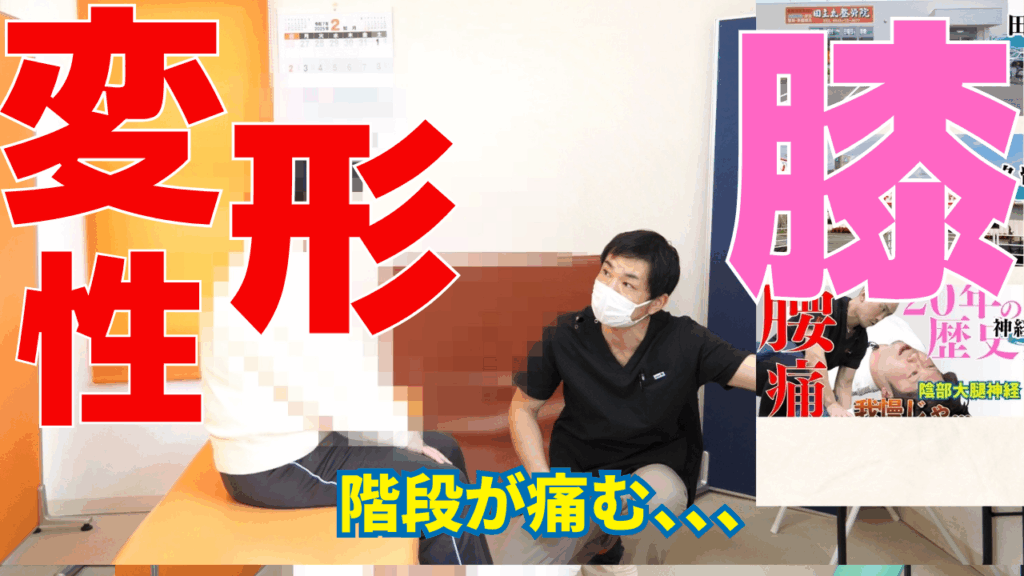
神経系ストレッチとは、正式には「神経モビライゼーション(Neural Mobilization)」または「神経フロッシング」とも呼ばれ、筋肉や関節ではなく神経そのものを対象とした特殊なストレッチング法です。
神経系ストレッチの目的
神経は身体の中で筋肉や腱などの組織の間を走行し、さまざまな原因で圧迫されたり動きが悪くなったりすると、痛みや痺れなどの症状を引き起こします。
神経系ストレッチは、以下の目的を持っています。
- 神経の滑走性や伸張性を改善
- 神経の圧迫を軽減
- 痛み・痺れ・違和感の改善
- 日常生活動作の向上・回復促進
通常のストレッチとの違い
筋肉の柔軟性を改善する通常のストレッチとは異なり、神経系ストレッチでは神経自体の可動性(滑走性)を改善することが目的です。
神経は筋肉や筋膜などの組織の中を滑るように動くため、この「滑走性」が障害されると、さまざまな不調の原因となります。
神経系ストレッチが有効な症状
主に神経の圧迫や可動性低下が関係する症状に効果的です。
- 坐骨神経痛
- 腰痛・臀部痛
- 股関節痛・膝痛
- 首や肩の痛み・腕のしびれ
- 手根管症候群・肘部管症候群
- 頭痛(特に頚椎由来)
神経系ストレッチの種類と代表的手法
代表的な手法として以下のようなものがあります。
- スランプテスト(Slump test)
- 坐骨神経の滑走性を改善するストレッチ。
- 背中を丸め座位で膝を伸ばし、頭を前に倒して神経を伸ばす。
- SLR(Straight Leg Raising)
- 仰向けの状態で片脚をまっすぐ挙上することで、坐骨神経にストレッチを与える方法。
- 上肢テンションテスト(ULTT:Upper Limb Tension Test)
- 上肢の神経(正中神経、橈骨神経、尺骨神経)の滑走性を改善するための動き。
- 腕を伸ばしたり、手首を反らしたりすることで神経を伸ばす。
神経系ストレッチが効く仕組み
神経系ストレッチが効果を発揮する主なメカニズムは以下の通りです。
- 神経の滑走性回復
神経とその周辺組織との癒着や滑走不良を改善し、神経自体がスムーズに動けるようにすることで、痛みやしびれの改善を促します。 - 血液循環の改善
神経周辺の循環を改善し、酸素や栄養の供給を促進。回復を早めます。 - 神経の感受性の低下
過敏になった神経の感受性を下げることで、慢性的な痛みや痺れを軽減します。
神経系ストレッチの注意点と禁忌
神経系ストレッチは慎重に行う必要があり、無理に伸ばすと神経への刺激が強くなり、症状を悪化させることもあります。
特に以下のようなケースでは注意が必要です。
- 重度の椎間板ヘルニアなど、神経症状が強い場合
- 骨粗しょう症や骨折後の回復期
- 手術直後の回復期
- 炎症が強く急性期の症状がある場合
これらの場合は専門家の指導のもとで行うことが望ましいです。
実際の治療現場での活用例(症例紹介)
神経系ストレッチ福岡久留米では、神経系ストレッチを用いて次のような改善例があります。
- 坐骨神経痛や腰痛で歩行困難だった患者さんが数回の神経系ストレッチで劇的に改善し、日常生活に復帰したケース。
- 膝の打撲後に痛みが長期化していたケースで、伏在神経や大腿神経への神経系ストレッチを行ったところ、数回で症状が消失したケース。
このように、神経系ストレッチは多様な症状に対して即効性があり、治療効果が高い方法として整骨院や整体院で注目されています。
まとめ
神経系ストレッチは、神経の滑走性を改善することで痛みやしびれを解消する画期的なストレッチ法です。
ただし、自己流で行うと逆効果の場合もあるため、必ず専門家の指導の下で行うことを推奨します。